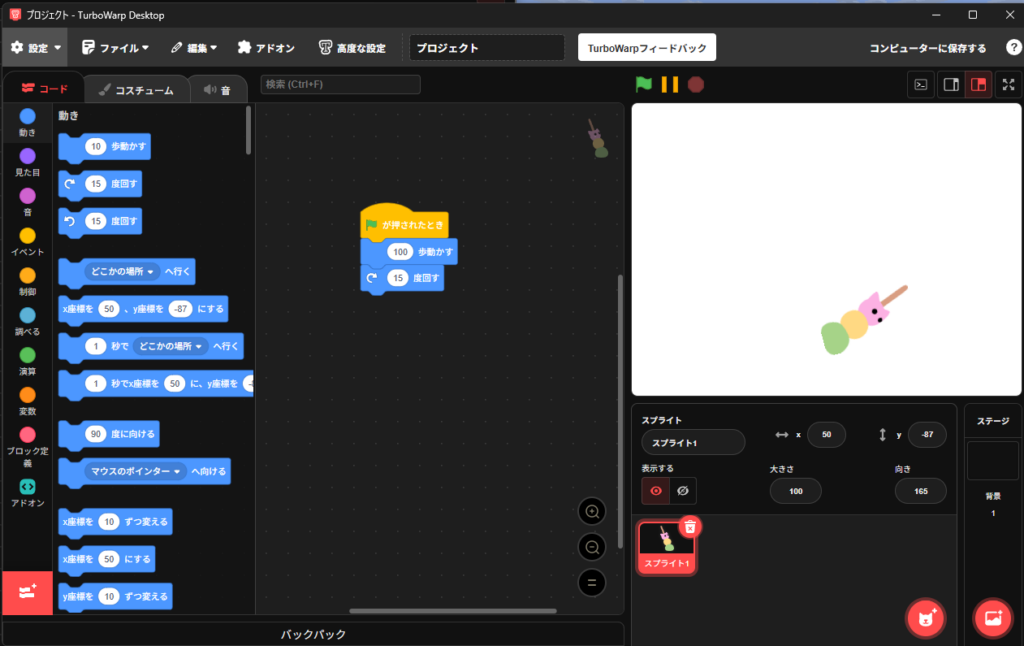Minecraft: Education の「ブロックコーディング×Agent(作業ロボ)」体験を JAVA版マイクラで再現
子どもがプログラミング体験教室で触れた Minecraft: Education の「ブロックコーディング×Agent(教育版の作業ロボ的キャラ)」学習体験がとても好評だったので、家庭でも“ほぼ無料”で再現できないかを検討しました。Minecraft: Education はライセンスが必要で個人契約のハードルが高いため、今回は Java版のマインクラフトで自前のサーバ(paper)を建て、サーバ側の拡張(プラグイン)だけで「ブロックコーディング×Agent」を再現する方針としました
Paper が何者か・他方式との違いは、過去の比較記事にまとめています:
→ マインクラフトサーバの構築方法:子どもと学ぶためのPaperサーバ構築ガイド
本記事ではこの Paper(Java版サーバ) を土台に、Scratch互換の TurboWarp と MCPQ(Paper用プラグイン+Pythonクライアント)
をWebSocket+Pythonブリッジでつなぎ、クライアント無改造・追加ライセンスなしで「ブロックコーディング×Agent」を再現する方針を整理します。まずは、その考えに至った経緯をまとめました。
TurboWarpとは:Scratchを高速・拡張可能にした環境
今回のプロジェクトでは、ブロックコーディング環境として TurboWarp(ターボワープ) を利用しています。
TurboWarpは、MITが開発したScratchをベースにしたオープンソースの派生プロジェクトで、次のような特徴があります。
- ブラウザ上で動作し、インストール不要で使える(今回は、Turbowarp Desktopアプリを入れて使う予定)
- Scratchのプロジェクト(.sb3)をそのまま読み込める
- JavaScriptで書かれた「拡張(extension)」を自由に追加でき、外部デバイスやWebサービスと連携できる
- Scratchよりも実行速度が高速で、実験的な用途や外部通信を伴うプロジェクトに向いている
Minecraft: Education Edition の「MakeCode」もブロックコーディング環境ですが、MakeCodeはマイクロソフトが管理する教育用専用環境であり、Java版マイクラとは直接つながりません。
そのため、Java版のPaperサーバと連携するには、自前で通信できるブロック環境が必要でした。
TurboWarpでは、JavaScript製の拡張を作成して、WebSocketやHTTP通信を直接扱うことができます。
これを活用することで、「ブロックからMinecraftサーバへ命令を送る」という構成を簡単に実現できると考えました。
“ほぼ無料”とした理由
- 使う主要コンポーネント(Paper/TurboWarp/MCPQ)は無償。
- ただし ゲーム本体の入手(買い切り or サブスク)は別途かかるため、表現を“ほぼ”にしています。
この記事で目指すこと
- 導入コスト:0円(ライセンス課金なし/オープン構成のみ)※マイクラを遊ぶためのライセンスは必要
- 学習互換性:Scratch相当の操作感(TurboWarp でブロック実行)
- 体験価値:Agent っぽい見た目と動き(高さ1マスのアーマースタンドを“疑似エージェント”に)
- 運用簡素化:3操作(召喚/操作/片付け)に収束
候補の洗い出し
家庭学習で「ブロックコーディング×Agent」的体験を得る方法を比較します。
| # | 案 | 前提/対象 | Scratch
|
互換UI | Paper
|
対応 | Agent相当 | 料金 | 日本語 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft Education + MakeCode | Education/
|
Bedrock | ◯
|
MakeCode | × | ◯ | 公式Agent | 有償 | ◯ | ||||||||||||
| 2 | VisualModder | Java
|
(Spigot/Paper互換) | △ Blockly |
◯ | — | 無料 | × | (現状) | |||||||||||||
| 3 | マイクラッチ | Java
|
(配布形態依存) | ◯ Scratch系 |
不明 | — | 書籍や | 講座経由 | ◯ | |||||||||||||
| 4 | 今回の構成:TurboWarp + |
Java
|
(Paper) | ◯ | Scratch互換 | ◯ | ◯ | 疑似Agent | 無料 | ◯ |
※表の評価は本記事の調査時点・体験基準。将来の更新で改善される可能性があります。
それぞれの“推し”と“惜しい”
| # | 案 | 推し | 惜しい |
|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft Education + MakeCode | 公式Agent・教材資産が圧倒的。 | 個人は有償。Java世界(Paper)に持ち込めない。 |
| 2 | VisualModder | 無料・Java/Paperベース・設置系の作図が速い。 | 日本語UIなし、Agent的なNPC/エンティティ前提ではない。子どもの“歩くロボ体験”づくりに一工夫いる。 |
| 3 | マイクラッチ | Scratch系UI・日本語。 | 一般配布が前提でない(書籍・講座ルート)、Paper前提の体系的解説が少なめ。 |
| 4 | 今回の構成:TurboWarp + |
無料/日本語/Scratch互換。Agentっぽい表現(アーマースタンド)が作れる。Paperで横展開容易。 |
最終結論
#4のTurboWarp + MCPQ + Paperを試してみることにしました。
TurboWarp(ブロック) → WebSocket → Pythonブリッジ → mcpq-python → MCPQ(Paper)
の一本配線で、“Scratch互換UI × Java版 × 無料 × Agent的体験”を成立させます。
見た目の“Agent”は小型アーマースタンド(Small:1b)を採用し、歩行っぽいポーズ切替+微小移動で演出。
ブロック設置はエージェント前方に setblock ^1 ^ ^ で直感操作。ブロック名は日本語→ID辞書でラクに。
だれが幸せになるか(ユースケース)
- 家庭学習:学校のScratch経験がそのまま活きる(TurboWarp)。課金不要で続けやすい。
- 保護者/先生:無料でマイクラサーバ環境。Paperなのでマルチ環境・プラグイン連携がしやすく、サーバ運用ノウハウも流用可能。
- 子ども:“前へすすむ/右をむく/置く”がブロックで書け、“歩くロボ”が目で追える。
懸念と対策
セットアップの手間:dockerでコマンド一発で構築を目指す。安全性:WS/gRPCをlocalhost限定に。WAN公開はNG。- Agent本物ではない:Educationの“Agentエンティティ”とは別物 → 見た目と体験で寄せる(小型AS+発光+SE)。
- 教材資産:公式教材ほど豊富ではない → 自作テンプレを積み増し(迷路、橋架け、スタンプアート等)。
実装の全体像
PaperにMCPQを導入(plugins配下)。Pythonブリッジ:spawn / move / turn / place / despawnの5 API日本語→ID辞書を同梱(例:「白色の羊毛」→ white_wool)- TurboWarp:
- WebSocket拡張で ws://<mcpq bridge server>:8765 に接続
- ボタン(またはプルダウン)で操作を選び、JSONを送信
- 歩行演出:
- アーマースタンドのPose を2フレーム切替 → ^0.25 ずつ前進
まとめ
- visualmodder は“建築ブロックエディタ”として優秀だが、日本語とAgent的体験が弱い。
- Educationは有償が壁。
- 結論:TurboWarp +
MCPQ +Paper なら 無料・日本語・Scratch互換で、“Agent っぽい”体験まで作れる。
次回はそのまま動く テンプレと セットアップ手順を公開します。
(追記 2025-11-08)構成を簡素化しました
当初は「TurboWarp →(WS)→ Pythonブリッジ →(gRPC)→ MCPQプラグイン → Paper」としていましたが、WebConsole系プラグインに直接WebSocketで接続することで、Python/gRPCの中間層を省略できました。
これにより、TurboWarpから送った文字列=サーバコンソールコマンドとして即時実行されるため、擬似Agent(小型アーマースタンド)の召喚/移動/回転/設置などはよりシンプルに実現できます。
一方、ブロック情報の取得やイベント購読など高レベルAPIが必要な場面では、従来どおり MCPQ の採用(または併用)が有効です。用途に応じて選択します。
セキュリティに注意:WebConsole系は強力です。127.0.0.1 バインド、認証、プロキシ側での制限などを必ず設定してください。